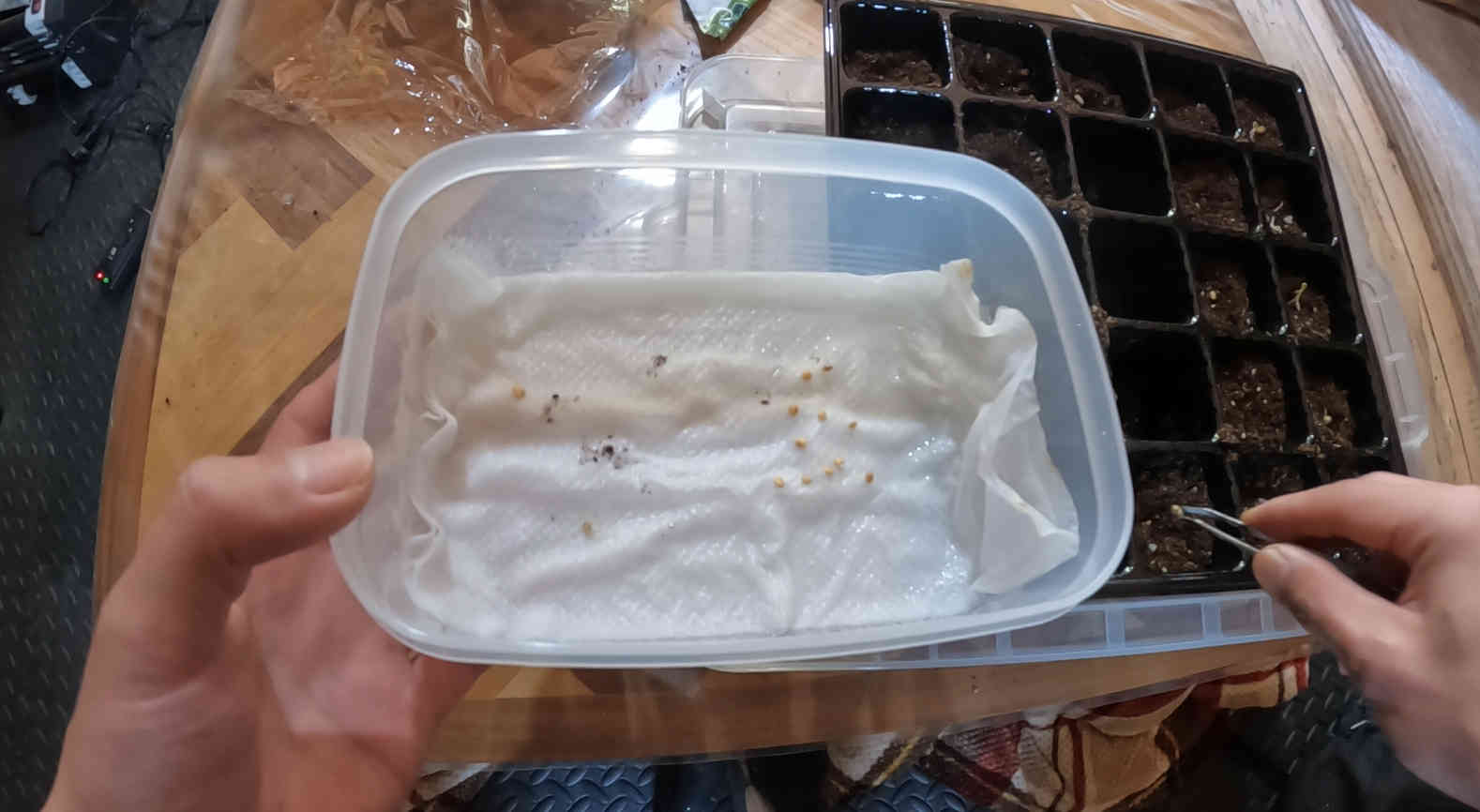どうも、たかしです。
去年の9月に耕作放棄され荒れ果てていた農地を開墾し、10月の初めに初めての作付けを行ってすでに半年が経過しました。

初めての野菜作りと言うこともあり不慣れで、めちゃくちゃ上手く行ったとはお世辞にも言えませんが、それでもそれなりの量の野菜が収穫出来て、この冬の食卓を大いに彩ってくれました。
秋~冬野菜の素晴らしいところは、葉野菜を畑に植えっぱなしにして長期保存ができるということ。白菜なんかはついこの2月頭ぐらいまでずっと畑に放置していて、流石にちょっと痛んではしまっていたのですがそれでも問題なく食べることができました。
さて、そんな現在の畑の様子はと言うと……

ご覧のように、エンドウ以外の野菜は全て収穫が終わり、すっからかんとなってしまっています。

こちらはハクサイの残骸。右下はちょっとだけ残っていた芯から芽が出てきていますね。生命力が凄い。

こちらはシュンギクの跡地。マルチの穴から雑草がコンニチハし始めています。

こちらはホウレンソウ。全て収穫したと思っていたのですが、右上にちっちゃいホウレンソウの株が残っていましたね。
収穫し損ねたちっちゃい芽が生き延びていたのでしょう。

こちらはラディッシュ。もう12月中にはラディッシュは全て収穫し終わっていたので、他と比べても雑草の繁茂が酷いと思いきや……

こちらにも小さな芽が生き延びて、何と若干根を膨らませ始めていました。一体どこから出てきたんだか……

こちらはエンドウ。種まきが早すぎて成長しすぎてしまったため全部刈れてしまうかと思ったのですが、何とか生き延びています。枯れている部分も僅かなので、何とか収穫まで行けるかもしれません。
と言う訳で、今現在4畝中3畝が空いている状態となっていますので、来たる夏野菜の作付けに向けて、今回は空いた畝の土づくりをしていきます。
半年間もの間熟成されたコンポストトイレから作ったたい肥が、今回いよいよ炸裂します!
それではやっていきましょう。
関連記事
①マルチを外す

まずはマルチをすべて外していきました。
マルチの下に何かしらの生き物が隠れてて飛び出して来たら怖いなと思っておっかなびっくり外していきましたが、特に何もなく畝立てした当時のままの地面が底に残っていました。

すべて外した後がこんな感じ。見事にマルチの穴が開いていた部分だけ雑草が生えてきています。秋作と言うのもあるかもしれませんが、マルチの雑草抑制の効果は抜群ですね。
外したマルチは貧乏根性で使いまわそうかとも思いましたが、流石に劣化してきているのと、マルチ穴の幅も作付けする野菜によって異なるので、使い回すのは止めておきました。
種まき時期の関係で、マルチをかけてもしばらくは作付けしない野菜もありますし。
②天地返しをする

マルチを外した後の畝は十分ふかふかですが、それでも一旦全体的に耕し直して天地返ししておきます。
天地返しをしてで地表と地中の土を入れ替えることで、まだ栄養の残っている地中の土を表に出し、栄養が枯渇している地表の土を地中で休ませることができるはずです。
また、地中に潜んでいる害虫を表に出して、夜間の寒さに晒すことで除去することができるのも天地返しのメリットの一つです。山奥のこちらの土地は未だに夜中は氷点下になりますからね。

……と、思ったのですが、天地返しをしても目立った害虫は出てこず、ちょくちょく大きなミミズが出てくるぐらいでした。
教員時代に何回か授業で使う畑の土づくりをしたことがあったのですが、その時はヨトウガの幼虫がわんさか出てきたのが衝撃的だったのを覚えていたので、てっきり今回も出てくると思ったんですけどね。
ここら辺はヨトウガが少ないのかもしれません。
③土壌のph測定
ここで普通の土づくりの流れならば酸度調整のため灰などを畑にまくのですが、その前にまずはph測定をしていくことにしました。

こちらの簡易ph測定器で、土壌のph値が灰をどのぐらい撒く必要があるほど酸性に傾いているかをチェックします。
灰はアルカリ性の土壌改良材で、基本的に賛成に傾きがちな土壌のph値を中和する役割があります。ですが、もし土壌がそこまで酸性に傾いていない時に撒き過ぎてしまうと、土壌がアルカリ性に傾き過ぎて逆に作物を育てることができなくなってしまうのです。

足敵を使用する前には、まず土壌に十分水を染み込ませて……

その状態で地面に突き刺して、出た目を測ります。すると……

ph値は大体6.7~6.8ぐらいの値を示していました。
基本的に土壌ph値は6.0~6.5辺りが良いとされており、元々去年9月に開拓した際にはこちらの土壌ph値は6.8~6.9ぐらいだったので、若干酸性に傾いているとはいえ灰類を投入するほどでは無さそうです。
灰を投入する理由はph値以外にも他の栄養もあるので、できれば撒きたかったのですが……今回は止めておくことにしました。

ちなみに他の畝でも測定しましたが、やはり適正ph値以上の6.5以上を示しており……

もっとも酸性に傾いていたラディッシュの畑でもギリギリ6.5行かないぐらいでした。
やはり今回の野菜作りではそこまで大量の野菜を育てることができなかったので、その影響で酸性度の高まりも薄かったのかもしれません。
④コンポスト堆肥を投入する

灰の投入は今回飛ばして、いよいよコンポスト堆肥を畑に投入していきます。
半年間にわたって溜めて、そこから更に半年間にわたって熟成させたお手製のコンポスト堆肥が活躍する瞬間がやって来ました。

こちらが熟成半年のコンポスト堆肥の外観。1か月前に雑草を巻き込みつつ切り返しをしたばかりなので、結構雑草の形が残っていますが、かなりふかふかの土になっています。

コンポストトイレ由来とはいえ、成分のほとんどは土&雑草が分解された物なので、臭いは全く持ってただの土です。
完熟している牛糞ですら若干の臭いはする物なので、こちらは堆肥と言うよりは生ごみコンポストに使う基材に近い状態のように感じました。

畑を囲っている防獣ハウスの入り口には、獣が侵入できないよう地面に返しがあり一輪車が入って行けないため、入り口近くにビニールシートを敷いてその上に堆肥をまず移動させます。

その後、ビニールシートごと畝の上まで移動させ、堆肥をかけていきます。

その後、畝の土全体に堆肥が行き渡るよう、鍬で梳き込んでいきました。
すき込む作業は普通の鍬だとやりづらいので、備中鍬(先がフォーク型になっている物)が欲しくなりますね。裏庭の地面から先っぽの刃だけ出てきて取っておいてあるので、DIYで復活させるのもいいかもしれません。

エンドウ以外の3畝に均等に混ぜ込んで行ったのですが、残念ながらちょっと量が足りないような気がしました。
大体1㎡につき3~4kg堆肥だったら投入していく必要があるみたいなのですが、今回1畝で4~5kgぐらいしか投入できていないので、恐らく十分だとは言えないと思います。
とはいえ、コンポストトイレの量を増やすわけにもいきませんので、今後自家製堆肥の量を増やすための方法を他にも考える必要があるかもしれませんね。普通に牛糞とか購入してたら結構な費用になってしまいますから。

とりあえず現在投入できる分のコンポスト堆肥を投入していきました。
⑤次回、マルチ設置&その他園芸作業編に続く
今回は唐になった畝を解体し、新しくコンポスト堆肥を投入して土づくりしていく様子をお伝えしていきました。
堆肥を投入して1週間ほどは土を寝かしていく期間が必要みたいなので、この日の作業はいったん終了とし、マルチ設置やその他種まきやエンドウの支柱設置等はまた後日行うことにしました。
……と言うのが実は1週間前の話。なので次回はマルチを設置しその他園芸作業を済ませ、夏野菜に向けての準備を全て完了させていきたいと思います。次回、お楽しみに!
今回の記事は以上です。
また次回の動画でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。