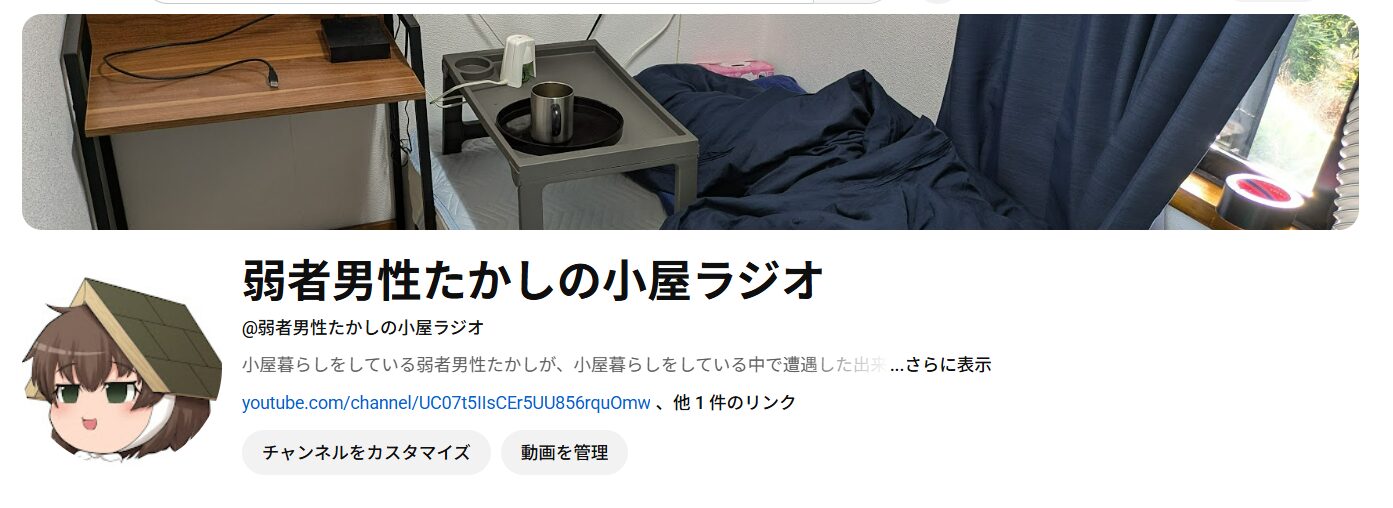本日YOUTUBE動画紹介記事も投稿しています。ぜひ併せてご覧ください。
どうも、たかしです。
飛び地に新たに畑を開墾して、自給自足に向けて新たな一歩を踏み出すシリーズの今回は第三回になります。
前回の内容では、草がボーボーな飛び地を草刈りしたり、下草でカッチカチになってしまっていた地面を鍬でひっくり返したりしていった様子をお伝えしていきました。


今回は前回整地をした畑予定地の周りに、シカやアナグマと言った獣が入り込まないようにするための「防獣ハウス」の骨組みとなる支柱を打ち込んだり、フェンスを取り付けていったりして、畑の完成に向けて作業を進めていく様子をお伝えしていきます。
それではやっていきましょう。
関連記事
①今回の防獣ハウス作成方針

今回もまた、支柱パイプと防獣フェンス及びネットを組み合わせて、周りを完全に囲う形で防獣ハウスを作成していきます。
正直今現在マジで資金難なので、天井まで囲ってしまうのではなくただ周りをフェンスで囲って地面からの侵入だけを防ぐ方式にして資材費の節約をしようかとも思ったのですが……。
でもそうすると、シカの飛び越え対策のためにフェンス高さを最低でも180㎝のものを設置しなくてはならず、それだけ高い柵となるとそれはそれでお金がかかってしまいます(安い防獣フェンスは150㎝高なので、その分延長しなければならない)。
ならば、防獣フェンス自体が低くても天井からネットを垂らして周囲を完全に囲む防獣ハウス型にした方が、費用面では多少高くはなってしまうのですが、シカの飛び越え対策にもなるし更には猿や鳥と言った通常の柵ではどうにもならない獣害にも対応できるということで、必要最低限の資材で、余っている資材なんかも流用しつつケチりにケチって防獣ハウスを作成していくことにしました。
②作成の様子
1.溝堀り

防獣フェンスを設置する際には、獣の地際からの侵入を阻むためにフェンスを埋めつつ設置する必要があるため、まずはそのための溝を掘っていきました。

相変わらず地面がカッチカチのため、予め鍬で周囲を掘り返して置いた後に……

スコップで掘り返し、溝を掘っていきます。

ぐるっと1周掘り返し、フェンスの設置準備が完了しました。
2.支柱を立てる

フェンスの支柱及び天井アーチの基礎ともなる防獣パイプを10本、周囲に設置していきます。

高さがガタガタになると天井アーチの安定性にもかかわってくるため、きちんと地面に埋める30㎝の位置でペンでマーキングしておいて……

畑の長辺部分に、1.5mごとに支柱を立てていきます。
フェンスの設置だけなら支柱は2m間でいいのですが、それだと恐らく天井にネットを取り付けた際にたわんでしまう可能性が高いので、1m間隔だと今度は資材費が高くつくということで中間の1.5m間にしました。

長辺両方に防獣パイプを設置したら、短辺部分には余っていた小さめの防獣杭を1本ずつ中間に設置していきました。
こちらは特に天井アーチの基礎になる物ではなく、あくまでフェンス設置のための杭なのでわりかし適当に設置していきました。
これで支柱の設置は完了です。
3.天井アーチの設置

まずはアーチパイプを防獣パイプの先に互い向きに取り付けまして……

さらにアーチパイプの先に横通しパイプを取り付けて延長し……

互いの横通しパイプが交わる地点に、棟ジョイントの接続部材を取り付けて天井アーチを作っていきました。
支柱になっている防獣パイプを見てもらうと分かると思うのですが、相当外側にたわませて無理やりアーチ状にしています。こうすることによってばねのように支柱パイプが内側に戻ろうとする力が働き、それによりアーチ部分の接続がより強固になるようにしています。

全ての向かい合っている防獣パイプを天井アーチで繋げ、計5つの天井アーチが設置されました。
このままの状態だと、一つ一つの天井アーチは独立してしまっており、一応先ほど説明した内に戻ろうとする力で支えられてはいる物の、強い力がかかると後々形が崩れてくる可能性があります。

そのため、防獣ハウスの強度を上げるためアーチ同士を棟部分に横通しパイプを取り付けて連結させていきました。

全ての天井アーチがこれで連結され一つになったところで、防獣ハウスの骨組みが完成しました。
本来であれば、これに加えて防獣パイプもまた横通しパイプで連結させてより強固にしたり、天井アーチの棟部分を支えるために支柱を追加したりといったこともする必要があるのだとは思いますが、資金難なので本当に最低限防獣ハウスの形を保つことができるギリギリのパイプ数だけで骨組みは完成させました。
これでも1万円以上かかってますからね。なかなか苦しい……。
4.フェンスの取り付け

骨組みが完成したところで、続いて防獣フェンスをハウスの周辺をぐるっと囲む形で取り付けていこうとしたのですが……

残念ながらこちら余り物の防獣フェンスだったため、途中で足りなくなってしまいました。

防獣フェンスはもう一つ余りがあるのですが、こちらはメーカーが異なり、先ほどのカイトン製のフェンスは高さ1.5mなのに対し、こちらのマタイ製の物は高さが1.2mしかありません。
この2種類を適当につぎはぎしてしまうと、最終工程の天井ネット取り付けの際に高さが合わず隙間ができてしまう可能性があるため……

短辺部分の1カ所を、まるっと高さ1.5mの方のフェンスをカットし取り外して……

そうすることで扉部分と、あと手前の短辺部分だけがフェンスの無い状態にすることができたので……

空いてしまった短辺部分に1.2m高さのフェンスを取り付けることで、後々天井ネットを取り付ける際に長さの調整がやりやすいようにしていきました。

フェンス全体の位置が決まったら、支柱一本一本にしっかり結束線でフェンスを固定していき……

扉部分には、地際からの侵入を防止するための返しのフェンスを取り付けたら……

最後に予め掘っておいた溝部分を再度埋め直して地際のすき間を無くし、フェンスの設置が完了しました。
5.扉の作成

開口部の扉を取り付ける際に一番いいのは、かつて庭を囲う際につかった「いのしし君」のようなワイヤーメッシュフェンスをそのまま取り付けてしまうことなのですが……

しかしいのしし君は一枚1200円とわりかし高価だし、コンパクトカーで運ぶことができないのでいちいちレンタルトラックで1枚のために往復して運ぶというのも割に合いません。
なので、カイトン製の高さ1.2m防獣フェンスの端材をつぎはぎして扉にしていくことにしました。

高さ1.2mしか無いため、1枚だけでは扉にするには高さ不足です。そのため、残っている部分全てを使い切り、開口部に合わせた長さで2枚を切り出して……

これまた資金不足丸出しなのですが、切り出した2枚のフェンスを竹を使って繋ぎ合わせて扉の形にしていきました。
本当だったら普通にパイプとか防獣杭とか使いたいんですけどね……マジで資金無いんですよ。

繋ぎ合わせて作った扉を開口部にあてがい、金具を使って防獣パイプと扉を固定したら……

完全にぴっちりとはいきませんでしたが、一応扉を取り付けることができました。
③次回「天井ネット取り付け→完成編」へ続く

今回は、畑予定地の周りを支柱とフェンスで囲み、防獣ハウスの骨組みを作成していった様子をお伝えしていきました。
最近随分涼しくなってきたので、屋外で思いっ切り体を動かせる開拓には最高の季節になってきましたが、それでもここ数日動き通しなのでかなりヘトヘトです。
去年の畑開拓記事とかだと、1週間以上かけている工程を3~4日で進めようとしている訳ですからそりゃ大変なんですよね……。
とはいえ、のんびりダラダラ開拓している余裕が僕に無いのも事実ですので、一日でも早く新しく野菜を栽培できるようにするため、次回完成を目指して急ピッチで作業を進めていきたいと思います。
今回の記事は以上です。
また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。
↓ランキングに反映されますので、よろしければクリックお願いします!